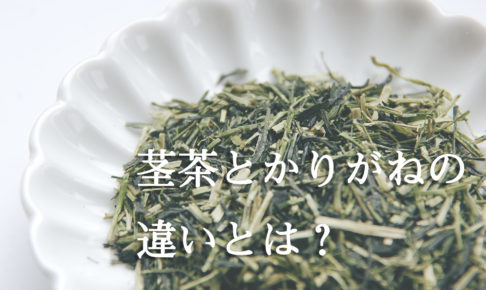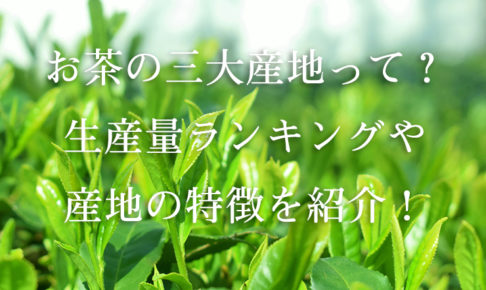白川茶は岐阜県の一部で生産されているお茶のブランドで、高級煎茶の銘柄として知られています。
生産量が少ないため、名前は聞いたことがあるものの、実際に飲んだことはないという方も多いのではないでしょうか。
そういった方のためにこの記事では、白川茶の歴史や特徴について解説していきますので、ぜひご覧ください。
白川茶とは?
まずは、白川茶がどのようなお茶なのかを解説していきます。
美濃白川茶
白川茶とは、岐阜県で生産されるお茶のブランドです。
岐阜県内で生産されるお茶を総称して美濃茶と呼ばれていますが、美濃茶の中にもいくつかブランドがあり、岐阜県西部で生産されたお茶は美濃いび茶、東部で生産されたお茶は美濃白川茶と呼ばれています。
白川茶とはこの美濃白川茶のことを指しており、2008年に美濃白川茶として特許庁の地域団体商標に登録され、ブランド化が図られるようになりました。
産地
すでにご紹介したように白川茶の産地は岐阜県の東部にあり、主な産地は白川町と東白川村周辺です。
岐阜県で白川といえば、白川郷を思い浮かべる方も多いかと思いますが、白川茶の産地は白川郷のある地域とは別の地域です。
白川町周辺 は、昼夜の寒暖差が大きいことや水はけのよい土壌など、お茶の栽培に適した条件がそろっており、上質な茶葉が育ちます。
新茶の時期
白川茶の新茶の時期は、5月上旬から中旬にかけての時期です。
暖かい地域では4月の上旬から新茶の収穫が始まりますが、白川茶の産地は涼しい気候のため、5月に入ってから収穫が始まります。
その年によって若干前後することもありますが、新茶の収穫後、1か月程で新茶で作られたお茶が店頭に並び始めます。
歴史
白川茶の正確な起源は不明ですが、1687年に書かれた書物に白川茶に関する記述が残っており、少なくとも400年以上前から、お茶の生産が行われていたことがわかっています。
伝承では東白川村の蟠龍寺というお寺の住職が、京都からお茶の種を持ち帰り、周辺の住民に薬用にと栽培をすすめたとされています。
現在、蟠龍寺は残っていませんが、跡地につづく参道には今もお茶の木が残っており、大門茶というお供え用のお茶として栽培されています。
白川茶の種類

白川茶の多くは煎茶に加工されますが、それ以外にも様々な種類のお茶を生産しています。
ここでは、白川茶の主な茶種をご紹介します。
煎茶
煎茶は日本茶の中で最も多く生産されているお茶で、旨味と日本茶らしい渋味が特徴です。
煎茶は蒸気で茶葉に熱を加えた後、揉みながら乾燥させて作るお茶で、玉露や番茶、かぶせ茶なども基本的には同じ方法で製造されます。
白川町周辺は恵まれた気候から、品質の高い茶葉が育ちやすく、その多くが高級煎茶として販売され、お茶の品評会でも高く評価されています。
ほうじ茶
ほうじ茶は、茶葉を高温で焙じて(焙煎)作られるお茶で、焙煎による香ばしい香りが最大の特徴です。
高温を加えることによって、茶葉に含まれるカフェインの量が少なくなるため、刺激の少ないお茶として注目されています。
一般的にほうじ茶は、新茶より後に収穫される番茶を原料とすることが多いですが、白川茶の中には新茶から作られたほうじ茶も販売されています。
抹茶
抹茶は煎茶とは異なり、茶葉を揉まずにそのまま乾燥させて作られる碾茶(てんちゃ)を粉末にしたものです。
抹茶は渋いお茶というイメージを持たれることもあるようですが、実際は渋味が少なく、甘味のあるまろやかな味わいです。
白川町周辺で抹茶が生産されるようになったのはごく最近のことで、地元の町茶業振興会を中心に2015年から抹茶が生産されています。
茎茶
茎茶は、煎茶や玉露を製造する工程で、茶葉(本茶)と選別された茎を集めたもので、ほのかな甘味があります。
お茶にはテアニンという甘味成分が含まれていますが、テアニンは茶葉よりも茎に多く含まれているため、茎茶には本茶以上の甘味があります。
また、テアニンにはリラックス効果もあるため、気分を落ち着けたい時にも茎茶はおすすめです。
白川茶の特徴

白川茶の特徴は、高地で生産されていること、高級煎茶が多いこと、渋味が少ないことの3つです。
ここでは、それら3つの特徴について詳しく解説します。
高地で生産
白川茶が生産されているのは、白川町や白川村周辺の山間部です。
標高200mから700mの山の斜面に茶園があり、適度な湿度と昼夜の寒暖差から霧がかかりやすいため、日照時間が短くなります。
白川町周辺は、平野部と比べると日照時間が短く、茶葉がゆっくりと成長するため、茶葉が軟らかくなります。
高級茶が多い
白川町周辺では煎茶の生産が盛んですが、茶葉の品質が高いことからその多くは高級煎茶として販売されています。
これまでに十数回農林水産大臣賞や天皇杯などを受賞しており、生産量こそ少ないものの、良質なお茶の産地として、高く評価されています。
渋味が少ない
白川茶には、渋みが少ないという特徴があります。
白川町周辺は日照時間が短いことを先に解説しましたが、これにより渋みが少なくまろやかな味わいのお茶が育ちます。
お茶の渋味はカテキンという成分によるもので、カテキンはテアニンが日光に当たることで合成されます。
日照時間が少なく、茶葉に当たる日光が少なければ、カテキンが少なくテアニンが多い茶葉が育つため、渋味も少なくなります。
白川茶の入れ方

白川町周辺で生産が盛んな煎茶と、ほうじ茶をおいしく飲むための入れ方をご紹介します。
煎茶の入れ方
煎茶は数回煎じることができますが、急須の中にお湯を残したままにしておくと、次に入れる際に渋くなってしまいますので、必ず最後の一滴まで茶碗に注ぎましょう。
分量(1人あたり)
- お湯 80ml
- 煎茶 2g
入れ方
- 急須にお湯を注ぎ、その湯を茶碗に移して急須と茶碗をあたためる
- 用意した煎茶を急須に入れ、茶碗のお湯を急須に戻す
- そのまま1分程待つ
- 少しずつ廻し注ぎする
- 2煎目以降は、急須に直接お湯を注いで入れる
2煎目以降は1煎目よりも味が出にくく、高温で入れる必要があるため急須に直接お湯を注ぎます。
ほうじ茶の入れ方
ほうじ茶の香ばしい香りを愉しむためには、香りが立つように高温のお湯で入れるのがポイントです。
分量(1人あたり)
- ほうじ茶 2g
- お湯 80ml
入れ方
- 急須に人数分のほうじ茶を入れる
- ポットから急須に直接お湯を注ぐ
- そのまま30秒ほど待つ
- 少しずつ廻し注ぎする
- 2煎目以降は1分ほど浸出させる
この入れ方はほうじ茶だけではなく、番茶や玄米茶を入れるときにおすすめです。
まとめ

- 白川茶とは、白川町と東白川村周辺で生産される美濃白川茶を指す
- 白川茶の新茶の時期は、5月上旬から中旬頃
- 白川茶には、高地で生産されている、高級煎茶が多い、渋味が少ないという特徴がある。
白川茶の歴史や特徴について解説しました。
白川茶は生産量が少ないお茶ですが、興味のある方は一度試してみてはいかがでしょうか。
他の産地についてもっと知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。